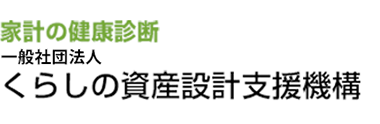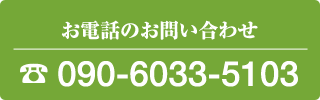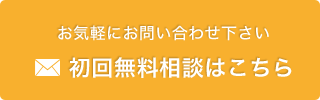2018年09月16日(日)
介護というとまず対応を迫られるのが親の介護、そしていずれは自分自身の避けて通れない課題です。 急速に進む少子高齢化は介護問題に大きな影響を与え介護は様々な面で少子高齢化に対応する進化を求められています。 少子高齢化が進んだのは、ご存知のように高齢者の平均寿命が延びた一方、生まれてくる子供が減ったためです。高齢者の平均寿命は2016年には男子80.98歳、女性87.14歳にまで延びて・・・
記事を読む »
2018年09月10日(月)
国民の暮らしを守る社会保障制度はどのように発展してきたのか、そして今どのような課題を抱えているのでしょうか? 社会保障制度は、第二次大戦後に整備され始めた当初は、貧困な状態にある人々を救済するための公的な仕組みとして認識されていました。 社会保障制度審議会勧告(1950年)は「国民の生活はあまりにも窮乏であり、いかにして最低でいいが生きてゆける道を拓くべきか、これが基本・・・
記事を読む »
2018年09月10日(月)
認知症などにどう備え、どう対応するかは大きなテーマですが 対応方法の一つである成年後見制度の基礎についてお伝えします。 成年後見制度は判断能力が不十分な人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を本人とともに支援者である成年後見人等が行うことで、本人の意思や自己決定を尊重しながら本人を保護する法律上の制度です。制度は法定後見制度と任意後見制度に分けられ、法定後見制度は・・・
記事を読む »
2018年07月20日(金)
保健医療の分野では、日本の医療と福祉の関係は医療費の自己負担を軽減する公費による経済保証が主なものでした。しかし、社会の高齢化により医療費が高騰すると、長期入院を問題視し退院の促進と在宅医療への移行が推進されるようになりました。社会福祉の領域では施設福祉から地域福祉へ重点を移す動きが強まりました。在宅福祉サービスを充実させるために介護保険制度が導入され、住み慣れた地域・・・
記事を読む »
2018年07月03日(火)
先日住宅ローンのご相談を受けた若いご夫婦は、家計をしっかり管理、堅実なライフプランニングづくりに取り組まれていました。相談内容は2社の金利固定期間10年の固定金利期間選択型35年ローンのどちらが良いか?というもの。金利の安い変動金利型も選択肢に入れていらっしゃるという事でした。 変動金利型はA社が金利0.725%で、金利優遇―1.85%。B社が金利0.77%で金利優遇―1.6%。一方10年の固定・・・
記事を読む »
2018年07月02日(月)
相談ではご本人だけでなくご家族の老後の暮らしなどについて、経済面だけでなく、認知症など健康面に話が及ぶこともしばしばです。ご家族の介護をされた方はよくご存じでしょうが相談、これから対応という場合はまず、認知症や身体的な機能の低下などについて知るところから始めなければなりません。 認知症は、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症,レピー小体型認知症、前頭側頭型認知症などに分類され、多くの認知症に・・・
記事を読む »
2018年06月25日(月)
ファイナンシャルプランナーは老後に備えたライフプランニングだけでなく、親の介護や福祉サービスなどについても相談されることが少なくありません。人生100年時代を迎え、高齢者の心身の状態について確かな認識を持っていることが必要となってきています。 高齢者になると加齢による身体の衰えに加え、長年の生活習慣を原因とする不調が重なり高齢者に多い病気を発症するケースが多くなりま・・・
記事を読む »
2018年04月18日(水)
「銀行にお金を預けても金利が低いのでメリットがない。」ほとんどの人の実感ではないでしょうか?ここ数年インフレ率は1%以下と低いレベルで推移していますが、これ以上に低いのが銀行にお金を預けた場合の金利です。超低金利政策で金利がインフレ率より低いため、お金を銀行に預けていると、元本保証の預金であっても実質的にはお金が徐々に目減りしてゆくことになります。今後、インフレ率が高ま・・・
記事を読む »